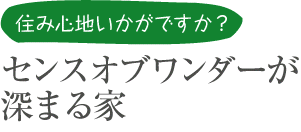インタビュー/2010年10月
滋賀県大津市
記者/塩見直紀
■ 2009年4月入居
2009年、マンション生活から一転して住暮楽にてOMソーラーの家を新築。現在、敷地内の畑を耕して家庭菜園を楽しむなど、豊かな自然をいぱいに感じながらの生活。ご主人と奥様、二人のお子さまとの4人暮らし。
「いい家やな」
職場から帰るたび、主人は「いい家やな」と言うんですと奥さま。家族もきっとみんな同じ思いでしょう。築一年半だからではなく、きっとこれからもずっとその台詞をつぶやくのではないか。縁あって、OMソーラーの家に初めてうかがい、そう思いました。感想は、と言えば、たしかにこれは楽しいはずだなあ、というものです。家の一階も二階も、庭もすべてが楽しい。ぼくなりに篠崎家を分析し、ひとことで言うなら、「野性味のある家」。人間が家畜化していると言われている現代ですが、篠崎邸はなぜか違うようです。それはなぜか。取材中、こんなことばが出てきて、はっとしました。
いろいろ土地を探してきたけれど、「造成地はいやだった」というものです。
 |
 穏やかな昼下がり。インタビューが始まりました。 |
|---|

記者紹介
塩見直紀
(しおみなおき)
半農半X研究所代表。1965年京都府生まれ。大学卒業後、(株)フェリシモを経て2000年に半農半X研究所設立。21世紀の生き方として「半農半X」を提唱。NPO法人里山ねっと・あやべでは、綾部里山交流大学を企画・運営するなど、地域おこしにも取り組む。著書に『半農半Xという生き方』ほか、全国での講演活動も多数。
土地と赤い糸
どんな家に自分たちは住みたいのか。イメージが定まった篠崎さんは土地を探します。声をかけてもらった土地がなんと奥さまの友人だったことから、夢が一気に動き始めました。土地を買うと言っても、高額です。篠崎さんが求めたのは、人間が手を加え過ぎた宅地ではなく、野性味を帯びた場所でした。もちろん安いという理由もあります。購入前の土地の写真を見ると、草木に覆われていました。鎮守の森のそばで、空き地。斜面もあり、持ち主も管理に手を焼いておられたようで、実際に開墾した際は手で持てないくらいの大きな木の根っこの山ができたそうです。「ここがいい」と直感でわかった篠崎さん。いまは建っているからこそ、全貌が見えますが、あの段階でよく家を建てたときをイメージできたと感心しました。
三つの工務店に、「ここに家を建てたいのですが」と篠崎さんが相談すると、2社は土を盛ったり、手を加えることで費用もかさむ提案でした。住暮楽はどうかといえば、自然の形態をうまく利用した提案でした。できるだけ経費を抑えたい。そのためには手を加えないこと。手を加えないとは何もしない、放っておくことではなく、土地のよさを活かし、デザインすること。住暮楽の岸本社長は創業前、実兄の建売り不動産業の会社を手伝っていたことで様々な土地に接し、「見立て」の力がついていたようです。

一畝ごとの段々畑はご主人のアイデア

高低差を活かしたアプローチ
ミニ里山
土地は本来、野性味を持っているのですが、最近は土地に力が無くなってしまっています。ぼくは丹波の里山の地に住んでいますが、篠崎さんの土地は小さな里山にできる可能性を感じました。すぐそばが鎮守の森、大きな桜の木も見えます。生えていた竹も完全伐採せず、以前からあった栗の木もちゃんと残されていていました。取材時、子どもたちは友だちと栗拾い。竹を活かせば、家庭菜園にも利用でき、七夕もできますね。ダイニングからは風に揺れるサトイモが見えました。芽が出たから植えたんですよとおっしゃっていましたが、アジアっぽくて、すてきです。サトイモの大きな葉っぱに溜まった水滴を集め、それで墨を磨り、七夕の短冊に書くと字がうまくなるといわれてきました。そんなこともここだとできそうですね。だから、ここは知恵や技術も継承される小さな里山なのです。家の下が斜面になっています。それは普通、嫌がられたりするものですが、逆転の発想。それが返って、篠崎家の魅力をパワーアップさせています。いまの子どもたちは急斜面を登れなくなっているといいます。かつてあった「でこぼこ」の地がならされてしまっている日本ですが、ここには無くしてはいけないものがたくさん眠っていました。

緑のトンネルは子供達のお気に入り
レイチェル・カーソンの夢を継ぐ家
住暮楽の家に住み始めて、子どもたちに変化はありましたかと尋ねると、雲や夕焼け、月のことなど、空の様子について話すことが増えましたとご両親。ほかにも、冬でも裸足でいるとか、友だちを家に呼ぶ回数がとても増えたようです。雨でも家のなかは楽しいし、外は外でワンダーランド。遊びに来た子ども達は「わっ、木の家や」と言い、たいてい靴下をぬぐそうです。大人のお客様も素足になろうと靴下を脱ぐのが当たり前になる時代が来るといいですね。(笑)でも、これはなかなか本質的なことかもしれません。
『沈黙の春』で有名なレイチェル・カーソンは四十数年前、こんなメッセージを残しています。「生まれつき備わっている子どものセンス・オブ・ワンダー(sense of wonder=自然の神秘さや不思議さに目を見張る感性)をいつも新鮮に保ち続けるためには私たちが住んでいる世界の喜び、感激、神秘などを子どもと一緒に再発見し感動を分かち合ってくれる大人が少なくともひとりそばにいる必要があります、と。
篠崎邸はカーソンのいう感性を新鮮に保ち続けることができる家のようです。経費をすこしでも抑えたいという思いもあって、家族みんなで壁を珪藻土で塗られたそうです。世界広しといえども、家づくりに参加した人はまだまだ少ないでしょう。それも子どもも参加! 家族で壁を塗ったんだねという思い出は一生ものだし、お子さんのセンス・オブ・ワンダーをぐっと育んだことでしょう。

秋の恵みに感謝

やりたいことがいっぱい!アイデアがつきません。
家族が向かう次なる港
家族共有の書斎を住暮楽では「シップ/SHIP」と呼び、プランニング時には原則的に必ず盛り込むそうです。SHIPとは、「to share intellectual production」の頭文字をとったもので、「知的生産を分かち合う」場所、という意味を込め、名づけられたものです。篠崎家ではみんなその空間を「シップ」と呼んでいます。子どもたちは勉強したり、本を読んだり。夫妻は菜園のことをインターネットで調べたり、本で研究したり。ふと、思い出したのが、「家族全員が灯のもとに集う宵のひととき。みな思い思いのことに没頭しているのだが、それぞれが家族の存在を感じている」という東欧の哲学者タタルケヴィッチのことばです。個々は何かに没頭しているけれど、でもバラバラではなく、家族は愛に満ち、一体感がある。「シップ」をつくることで、未来を生きる知の力と感性を備えた家族になることを住暮楽さんは設計されているように感じました。
住暮楽のホームページですてきなメッセージがありましたので、紹介しましょう。「本棚には、子どもの教科書の横に、両親の本が一緒に並びます。親の読む本の背表紙をみて、子どもが何かを学び、また子どもの読む本を親も知る。お父さんのマイホーム残業、子どもの宿題、お母さんの家計簿…それぞれが違うことをやっていてもSHIPに集まって一緒にやれば、それが団らんです」。こんなことを考えてくれる工務店さんがあるのですね。

南側には大きな桜に木、春には花見もできます。

ロフトはこどもたちの隠れ家。
アイデアがいっぱい生まれる家
「ニホンミツバチはどうですか」と尋ねると、「そうなんです、飼えたらいいなと思っているんです」と。すると、本冊子編集者のお父さんが生前、養蜂もしていたので分離機もありますので使ってださいという声も飛び出し、びっくり。ついでに、我が家に眠っている杵臼も篠崎さん一家なら有効活用してくれそうな気がしています。
なんだかワクワクする家。どんどんアイデアが生まれる家。野生をすこし取り戻せる家。それはこの地に自然に従順な家を建ててくれた一家への「住んでくれてありがとう」という神さまからの贈り物かもしれません。
娘はビオトープがほしいようですとうかがったので、庭に小さな田んぼを作ったらと提案しました。「バケツ田んぼ」というのがありますが、ここなら、余った苗をビオトープとしての小さな開墾田んぼに、少し植えて育てるのもいいかもです。すると、カエルやトンボがやってくることでしょう。住まうことが後世への贈り物になる。地球へのささやかな恩返しになるといいですね。
これからもこの家や庭は深化していくので、ずっと未完成かもしれませんね、ということばが夫妻から出ました。ぼくはふと宮澤賢治のことばを思い出しました。「永久の未完成これ完成である」と。


家のどこにいても家族の存在が感じられる。